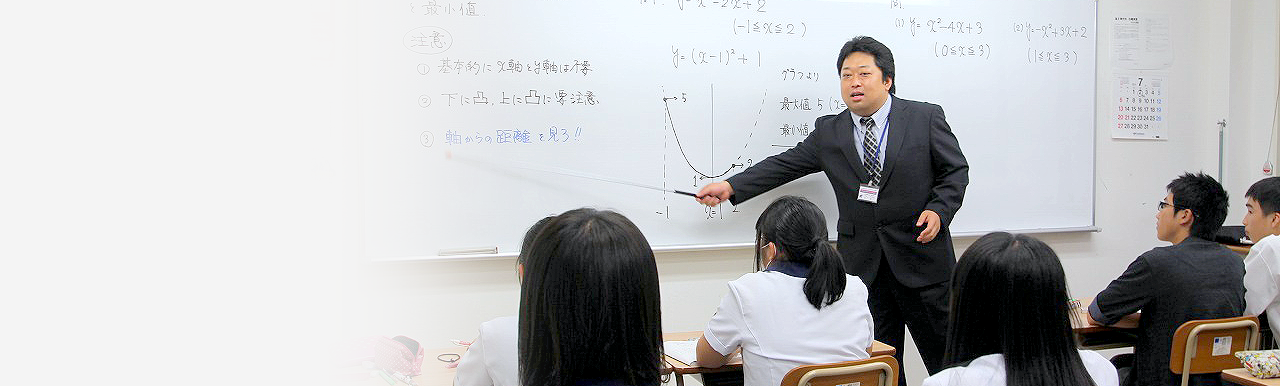
-
Blog ブログ
大学入試における「ウサギとカメ」
2025年09月06日
大學受験館カルタスです。
表題の「ウサギとカメ」というのは、イソップ寓話にも所収されており、みなさんご存知のあのお話のことです。あらすじは以下の通り。
”ある時、ウサギに歩みの鈍さをバカにされたカメは、山のふもとまでかけっこの勝負を挑んだ。かけっこを始めると予想通りウサギはどんどん先へ行き、とうとうカメが見えなくなってしまった。ウサギは少し疲れていたので、ウサギは少しカメを待とうと余裕綽々で居眠りを始めた。その間にカメは着実に進み、ウサギが目を覚ましたとき見たものは、山のふもとの先にゴールして大喜びをするカメの姿であった。こうして、カメのほうがウサギより速いということになった。(Wikipediaより引用)”
このお話の教訓は、一言で言うなら、油断大敵ということだと一般的には考えられているでしょうが、私はふと考えました。
「それって、自分がウサギの立場であるという前提で考えていることなのでは・・・?」と。
さて。
ゴールをどこに設定するか次第ではありますが、大学入試は過酷なかけっこ、どころではなく、過酷なフルマラソンです。高校3年生の1年間だけ頑張れば良いゴールを切れる・・・はずがありません。高校入試とは大きく異なり、大学入試は、あとでまとめて挽回のようなことが基本的にありません。高校1年生として入学してすぐから、望もうが望むまいが、大学入試に向けたマラソンは始まってしまっているのです。
そんな中で、高校入試までは自分よりも足の遅い「カメ」を尻目に、直前のラストスパートで余裕で(人によってはなんとか)合格というゴールテープを切った高校1年生が、自身を「ウサギ」なのだと考えてしまうことはふつうにあることでしょう。相対評価の中でそれほど努力をしなくても自分が優位に立てたり、ゴールテープを切ることのできる人数にゆとりがある競争(≒倍率が極端に低く、ほぼ間違いなく合格することがあらかじめ容易に推定できるような受験)においては、それも仕方のないことなのかもしれません。
ただ、大学入試という競争の中では少なく見積もっても日本全国40万人~45万人の全受験生の70%は、驚異的な速力を持つ「ウサギ」などではなく、「カメ」なのではないでしょうか。道中の模試成績、出願先の大学を最終的にどこにしたか(道中の志望大学がどこかではない)、そして実際の受験の合否結果(合格の場合の成績開示データも含む)などを考慮すると、私の直感はあながち的外れではないと思います。つまり、圧倒的な走力(=学力)を持つような、普通に走れば絶対にカメには負けないウサギのような高校生や、生徒自身の自己評価ほど走力(=学力)がある高校生は極めて少ないということです。自分は特別に秀でた「何者か」ではなく「ただの凡人」なんだと自己認識することはもちろん愉快なことではありません。しかし、1を聞いて10を知るような、物事を最速・最効率的に処理したり難なく長期的に暗記したりできるような、初見の難問でもその場で容易に解答を導いてしまうような、そんな天才は本当の意味ではごくごく一握りだと思います。ですので、「なぜ自分はそういう天才じゃないんだ・・・」と嘆いたり、「1日2日ちょろっと勉強してみたけどできない(天才ならできるのでしょうけど)」と僻んだりするのはポイントがずれています。
凡人でいいんです。継続的に努力できる凡人であれば。人よりも劣っていると思えば人よりも余分に努力できる精神を持って行動できる人であれば。
「カメ」が自らが「カメであること」を自覚せず、あたかも自らが「ウサギ」であるかのような立ち振る舞いをしていては、マラソンの中でどんどん先頭集団から置いて行かれますし、中団~好位置につけることすらも叶わなかったりします。なにしろ、大学入試においては、走っているウサギが多いからというよりもむしろ、自分よりも足が速くてさぼらず努力を継続するカメがわんさか走っているから過酷な競争なのだという認識を持たなくてはいけません。自称ウサギは多いですが実際は足が大して速くはないカメなのですから、カメが自由気ままにウサギのような怠惰な高校3年間を送れば、どうなるかは火を見るより明らかです。
私は「カメであること」を否定的に捉えているのではありません。むしろ、「カメであるのにウサギであろうとすること」が世の中に蔓延していることを危惧しています。つまり、現状の自分のままで満足していたい?から、客観的に要求される基準に自分を合わせる努力をしようとせず、なるべく楽に、嫌いなことはせずに楽しく、それでいて、なるべく良い(世間的に評価されるような)目標が叶ったらいいなぁというような、甘い理想論がはびこっているように感じているわけです。
以前から何度もブログで記していますが、現状の実力よりも背伸びをした目標を覚悟を持って設定することは何も悪いことではありません。むしろ、それによって努力に拍車がかかりさえすれば、それがその人の学力を向上させることにつながるでしょう。
ただ実際は、覚悟なき目標(覚悟のない目標?それは単なる願望だと断罪したいところです)をぼんやり持った「ウサギぶったカメ」になってしまっている高校生が多いです。ネットを調べれば今のご時世は「正解らしきルートや正解らしき解答」がすぐに提示されます。その場しのぎでよければですが、英文の訳や数学の解法も例えばChatGPTに入力すればすぐに答えてくれる時代です。極端に言うと、辞書を引くことも参考書を紐解くことも自分の頭で考えることもないような、自分で自らの記憶に留めようとする意欲や暗記能力が低い生徒の割合は20年前よりも増加しているのは間違いないでしょう。二極化が日本の至る所で広がっているように思います。大学入試も20年前とは大きく変わりましたが、読解力や計算力や論理的思考力や判断力など、そしてもちろん、それらを支える基本的な語彙・文法・公式等のありとあらゆる知識を問われるテストが課せられるという事実は一切変わっていません(※一部の入試形態や一部の特殊な大学などは除く)。
まずは「自分がカメであること」=「ウサギのように並外れたスピードで走れるわけではないこと」と向き合わなければいけません。そしてそれは、繰り返しますが、恥ずべきことでもなんでもありません。受験生の大半がそうなのですから。ただし、冒頭のイソップ寓話にもあるように、たとえ歩みが遅くてもそれを認めた上で、負けん気を持つこと。少しずつでも足が速くなるように鍛えながら、歩みを止めないこと。そして、こうと決めて、やるからには競争に勝つ!という強い気持ちで努力を継続すること。周囲の「ウサギぶったカメ」の怠けた行動に惑わされず、ゴールを見すえて前進し続けること。
最後に、ウサギとカメの寓話から得るべきだと私が思う教訓、というか意識づけ。
「本気を出したウサギ(ごく一部の天才たち)には敵わなくても、自分もこの話のカメのように、自称ウサギの怠けもののカメには絶対負けないように努力しよう!自分はウサギぶったカメにならないようにしよう!そういう姿勢で大学入試という高校3年間が舞台のマラソンを完走できれば、合否結果や進学先だけでは測れない人間的な成長を自分は遂げているはず!それが大学生~就職活動~社会人という長い人生のステージで自分を支える財産の1つになるはずだ!」
この境地に達しさえすれば、将来二度とすることはないであろう「英文和訳」や「微分積分」や大学入試で問われること全てが、自分という人間を一回りも二回りも大きくする上では決してムダなものではないと思うことができるでしょう。苦手なことだったり好きではないことにどう取り組むか、計画的にやるべきタスクを管理する上でどういう工夫をするか・・・etc…、学習から学べることや得られることは、なにもその教科科目の知識や技能だけではないと思います。もちろん、人には向き不向きはありますし、同じように努力すれば必ずみな同じ成果が得られるとも限りません。本当に精一杯努力した結果、何かに見切りをつけたり、何かを諦めたりすることはあってもおかしくはないと思います。ただ、ろくに努力もせず、「嫌いだから」「ムダだ」「意味ない」と不快なものから安易に逃げる癖を学生の間に付けてしまうことは決して好ましいことではないでしょう。就職後も楽なことだけ、好きなことだけ、サボりながら適当に、定時でしか働きません、で許されるなら話は違ってきますが、お金を払う側(客、子ども、学生)である間は目をつぶってもらえることが、お金をもらう側(労働者、大人)になった瞬間から厳しく咎められることがほとんどです。親身であるがゆえの厳しい言葉をかけてくれるうちはまだましです。ひどい場合は仕事ができない厄介な部下or同僚だとして邪険にされたり無視されることもありえます。そして、最悪の場合、解雇されることになります。
そういうことにも備える意味でも、大学入試に必要な学習を通して、今自分を鍛えているんだと言い聞かせて、高校3年間の学習と向き合ってほしいものです。
大學受験館カルタス 山本




